ジャワ島地震ルポ
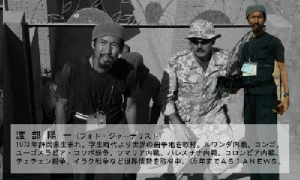
このページの記事はフォトジャーナリスト渡部陽一がASIANEWSウエブ向けに書き下ろしています。
![]()
インドネシア・ジャワ島地震
スマトラ地震の影響からも完全に復旧しない中、新たな震災が再び東南アジアで発生した。 2006年5月27日現地時間午前6時頃(日本時間午前8時頃)インドネシア・ジャワ島ジョグジャカルタで発生した地震は震源がジョグジャカルタ南南西25キロ、地震の規模をあらわすマグニチュードは6.3を記録。 インドネシア社会省によると被害は次のように報告されている。(数値は何れも6月6日現在)
被害状況・・・・人的被害 死者:5,857名 負傷者数:37,229名 避難民:423,720名 物的被害 家屋倒壊:84,643軒 家屋損壊:323,282軒
震災二日後に現地入りした渡部陽一の写真ルポをお届けする。
![]() 「震災の陽と影」5月30日
「震災の陽と影」5月30日
![]() 「届かぬ支援物資」5月31日
「届かぬ支援物資」5月31日
![]() 「被災地に見たインドネシア“らしさ”」6月1日
「被災地に見たインドネシア“らしさ”」6月1日
![]() 「ジャーナリスト・パラダイス」6月2日
「ジャーナリスト・パラダイス」6月2日
![]() 「被災者との生活」6月3日
「被災者との生活」6月3日
![]() 「運命」6月4日
「運命」6月4日
![]() 外務省ホームページ「インドネシアジャワ島中部における地震災害」
外務省ホームページ「インドネシアジャワ島中部における地震災害」
![]() リンク:渡部陽一のイラクリポート
リンク:渡部陽一のイラクリポート
「震災の陽と影」2006年5月30日
スマトラ沖地震から一年と半年。現地時間5月27日、朝5時54分、ジャワ島中部にてマグニチュード6.3の地震が勃発した。
ジャワ島中心分は州都のジョグジャカルタを中心に世界遺産の仏教寺院ボロブドゥール、ヒンドゥー寺院プランバナンが連なり、インドネシアきっての観光ポイントである。被害拡大が容易に推察できる状況であった。現地入りにあたってジョグジャカルタの国際空港は閉鎖されていた。日本を発つ段階でジョグジャカルタ空港にランディングできない場合は北方80kmにあるソロ空港に降りたつ手はずになっていた。実際には2日後にジョグジャカルタ空港は再開、世界中から救援物資が届けられ空港内は混雑を通り越し混乱していた。
日本からフライト8時間、バリ島のデンパサールを経由してジョグジャカルタ入りを果たす。ジョグジャカルタから震源地のパラントゥリティスまで距離で35km、一番の被害を被ったバントゥールまでは25km、 現地報道を見ている限りジョグジャカルタもすさまじき被害を被っていると想像していた。しかし空港から市内南部に位置するロッジ風の宿に移動するまで30分、車窓に飛び込んでくる風景は、屋台が連なり、食事をしている家族連れ、交通渋滞を巻き起こしているバイクや車、拍子抜けするほどどこにでもありふれる地方都市の面影そのものであった。ところどころ家屋が全壊しているものの、生活は普通に営まれていた。取材拠点となるホテルは一泊約12ドル。朝食つき(コーヒー、玉子焼きとミーゴレンと呼ばれる焼きそば)、自分以外にもメディア関係者やボランティア活動家の方々が多数宿泊していた。 宿舎のオーナーがジョグジャカルタの被害は一部すさまじきものがあるも、本当の被災地は南方に下ったバンドゥールエリアに集中していると語っていた。ホテルのスタッフの3分の2がそのエリアで家族が被害に巻き込まれたと語ってくれた。バントゥールでは特に水、食料、雨風をしのぐテントが不足していて、もしそのエリアに取材に入るのであれば、手助けできる物資を持参したほうがよいとアドバイスをくれる。ロビーで出会った方が静かにインタビューに答えてくれた。
「この地域は現在雨季ではないにもかかわらず地震が起こってから夕方雨が頻繁に降るようになった。大きな余震が続いていて、近いうちに再び巨大地震に襲われる、さらに郊外にあるムラピ山の火山が噴火してこの一帯溶岩で埋まってしまうであろう」。ジョグジャカルタ一帯、不吉な風説が飛び交っていた。
(6月9日更新)

被災地となったジョグジャカルタの街の俯瞰。

自宅が崩壊し、財産をすべて失った女性。
「届かぬ支援物資」2006年5月31日
ジョグジャカルタ市内のロッジ風ホテルに宿泊している。ホテル関係者は2階以上に宿泊するのは危険だと教えてくれる。地震がもう一度やってくる、二階にいたらそのままガレキに巻き込まれて死んでしまうからとにかく1階にいていつでも逃がれられるよう扉も開けておきなさいと。ジョグジャカルタ市内は街の中心部のスルタンパレス(王宮)を中心に北部と南部に大きく分けられる。宿泊先は震源地側の南部、この一帯は崩壊した家屋が目立ち、商店もシャッターをほとんど下ろしている。逆に北部はほとんど被害がなくレストランやホテルは普段通りの営業を行い、観光客の姿も多い。同じ街の中でこれほど違いが出ることには驚かされる。
最大の被害地、バンドゥールに入った。5000人以上がガレキの下敷きとなり、生き埋めとなった。バンドゥールに続く道は支援物資を運ぶトラックや家族の安否確認に向かうバイクでごった返していた。あたり一面の家屋はあたかもピンポイントの空爆を受けたかのように、完全崩壊している。各村々が地面から陥没したようにうずまっている。インドネシアの伝統建築様式が今回の被害拡大を促したといわれている。竹の柱を組み、レンガをくみ上げ厚さ一センチの瓦を屋根に敷き詰めるだけ。地震の横揺れ一発で壁と屋根が崩れ、竹の柱だけがあたかもジャングルジムのように残っている。コンクリートでできた近代的な建物は崩れ去ることなくそのまま姿を残していた。 崩壊した家屋をかいくぐって奥に進んでいく。被災者の口から聞こえてくる言葉はいつも決まっていた。食料が必要だ。水は何とか地下からくみ上げることができる。食料が全くない。支援隊が世界から集まってきていると聞いているが、どこにどのように届けられているかわからない。彼らを見たことがないんだ。この村には支援物資が届いていないんだ。バンドゥール役場前に野球場ほどの広さの緊急支援キャンプ地ができていた。インドネシア軍、マレーシア軍といった国際部隊、各国のNGO緊急支援団体のテントが所狭しと設営されていたが、物資の輸送には限界があった。各村々へつながる道は狭くトラックは入れない、奥地へは、へリコプターでポンプ式に物資輸送をしているが、限界がある。 最終手段は被災者みずからこのキャンプ地まで足を運んでもらうしかないということだった。物資はあるのに、届けられないジレンマにスタッフたちは頭を抱えていた。本日、午前8時45分に自衛隊緊急支援部隊先遣隊がジョグジャカルタに入った。ホテルでの打ち合わせのあと、即バンドゥールにある医療施設の視察に向かった。日本だけでなく、中国、韓国、マレーシア、シンガポール、アジア諸国の支援団体の姿が目立っていた。被災地ではスピードが命である。自衛隊活躍を追いかけたい。
(6月9日更新)

イモギリエリアでなくなった12歳の少女の遺影と墓地

ジャワ島地震で最も被害の大きかったイモギリでのインドネシア軍による復興作業。
「被災地に見たインドネシア“らしさ”」2006年6月1日
自衛隊医療部隊が午前10時、2機の軍用機でジョグジャカルタ空港に到着した。昨日の先遣隊が約20名、本体の医療チームは49名であった。プレスブリーフィングが空港敷地内で行われ、そのままホテルにチェックイン、午後15時からジャワ島東部にあるサンビピウ区域での復旧活動が開始された。現地のメディアも日本を始め世界各国の支援活動が特集し復興機運がたかまっていく。そして派手に活躍する支援団体以外にも、個人活動で被災者の生活基盤の復旧活動をしている人たちも多い。この地域には世界遺産を目的で観光に来る人たち以外にも、インドネシアの言葉や芸術を学ぶ学生が世界中から集まっている。彼らは自らも地震の恐怖を体験し、学校や地域でお世話になった被災者の為に現場に足を運び、ガレキ撤去や医薬品の運送を行っていた。被災者への思いやりという部分で印象深い出来事に遭遇した。
現地で雇った運転手兼通訳の男性と車で村が全壊してしまったイモギリ村の取材を終えてジョグジャカルタ方面に向かっていた。膨大な数の車がひしめき合い大渋滞を起こしている。渋滞で止まっているといきなり後方からバイクによる追突事故をおこされた。衝撃が激しく体が前に押し出され、危うくムチウチになるところであった。運転手がすさまじき剣幕で二人乗りしていた男性に詰め寄るも、非常にお互い穏やかに話をしている。話を聞いてみると追突した二人の男性は地震によって家屋が崩壊してしまい、放心状態でバイクを運転していた。注意が散漫な状態で衝突したのであり、まして地震の被災者であるのであれば彼らの想いを尊重しようということであった。車の後部はへこんでしまったものの、お互い助け合うことが重要であるという。やり取りを見ていて被災者はもちろん被害にあわなかった人たちも助け合いの精神、何よりジェントルマン心意気に深く頭が下がった思いであった。
ところで被災者やその家族はいったい何を食べて生き延びているのか?まさに現場での一番の疑問である。ジョグジャカルタ市内ではレストランが平常通りの営業をしていて、ナシゴレン(インドネシア焼き飯)ミーゴレン(焼きそば)などはどこでも格安に口にすることができる。それゆえにジャーナリストや外国人旅行者は被災地でありながらそれなりのグルメを楽しむことができる。村自体が陥没したイモギリ村の家族に密着したとき、一日のメニューを確認した。朝食インスタントラーメン、昼飯白米となすびの炒め物、夕飯白米とにんにくナス炒め、食後にスプーン3杯砂糖入りジャワティー。すべて瓦礫の下から掘り返した米であったり、親類から届けられた緊急食料であった。近所同士食料を持つものがなき者を賄っていた。助け合いの精神ここに極まれりである。
(6月10日更新)

支援物資をヘリで運びこむインドネシア兵士。

地震で家がガレキの山となってしまった男性は呆然と立ち尽くしていた。
「ジャーナリスト・パラダイス」2006年6月2日
現場においてカメラマンは撮影した写真を新聞社や雑誌社にネットを使って伝送する。撮影し、伝送して初めてすべてが完結する。それゆえにネット回線を確実におさえることが急務である。衛生電話回線で写真を送ることもできるが、今回は現地のローカルラインを使用した。地震で被害を受けた地でネットなどできるのかと意外に思われるが、人が集まる場所には確実にネットは存在する。ここジョグジャカルタでもネットカフェが多数存在していた。安心して写真を送ることができると高をくくっていたのであるが、いざ使ってみると恐ろしく速度の遅い回線で、かつブツリブツリと切断される。かつ日本語も読めずかけない。写真一枚送るのに10分はかかるであろうという代物であった。
それにしてもジャワ島地震の被害状況は地獄絵図そのものであるが、地震以前からジャワ島が旅行者に人気がある理由が取材中見えてきた。イスラム国家でありながらお酒を飲む風習が目立ち、かつ東南アジアでもずば抜けて物価が安い。食事は何を食べてもおいしい。ジャワの人たちは日本人のようにお辞儀をして相手をリスペクトする振る舞いが礼儀としてあり、笑顔を絶やさず非常に柔らかい物腰、治安のよさ、そしてボロブドゥール寺院を始めとする世界遺産といった見所、まさに地震がなければこれほどのパラダイスはないと感じる。フリーのジャーナリストにとって取材現場ではいかに取材コストを抑え、撮影を進行していくかが問題なのであるが、ここインドネシアはフリージャーナリスト来るべしの価格設定であった。 朝から晩まで車での移動を行っていた。地震被災地は半径25kmぐらいのエリアに集中していたので取材拠点の宿泊先から取材現場まで来るまで遠くても1時間という非常に撮影をスムーズに行える状態であった。道の交通渋滞とガレキで崩壊した路地をのぞけばストレスは感じない。時間がたてばたつほど、インドネシアが好きになってきた。 世界各国のガイドたちと共に仕事をするのであるが、毎度驚かされることがある。それは語学のセンスである。英語が母国語でない場所でも当然英語を話し、さらにドイツ語やフランス語を同時に使いこなす、こうした技量を持ったガイドたちが世界中に相当数いる。生活がかかっているゆえに死ぬ気で勉強しているのであろうが、4ヶ国語も5ヶ国語も使いこなすセンスには驚き、感心する。インドネシアの私のガイドも英語、ドイツ語、スペイン語を使いこなしていた。
(6月10日更新)
「被災者との生活」2006年6月3日
被災者の生活がどれほどのものなのか。現地で取材ベースキャンプ地にしているジョグジャカルタ市内にあるホテルで生活しているとその現状が見えにくい。取材を進めていく中で娘を瓦礫の下から掘り起こした家族に出会った。日々その家族の下に通ううちに、家族の人たちと同じテントでの完全密着取材をさせてほしいとお願いした。快く迎えてくれたのであるが条件がひとつあった。それは崩壊した瓦礫撤去作業を撮影の合間を縫って手伝うこと。男手が必要なのだという。カメラ機材やバッテリー類を詰め込んで彼らとの共同生活はスタートした。現地入りして一番疑問であったのは支援物資が届いていない地域の被災者が何を食べて生活しているのかということであった。
私が共同生活させていただいた家族は夫、妻、祖父母、生き残った下の2歳の娘の現在5人家族。12歳の長女は瓦礫に埋もれてなくなった。この家族の下には国際支援の物資は何も届いていなかった。救援部隊がどこにいて誰を助けているのか、わからないといっていた。その代わりに遠方に住む親類が食料を時々届けにやってきていた。被災者家族のメニューを報告する。朝食はインスタントヌードルを細かく砕いて湯がいたもの、ジャワティー一杯。昼食、なすびのぶつ切り油いためと瓦礫の下から掘り起こした白米を炊いたもの。夕食、やはりなすびの油いために昼に炊いて残したあった白米の残り物。就寝前、ジャワティー一杯、以上。これが毎日繰り返されていた。調理する妻は「今はこうしたものしか食べられない、食料がないのだから仕方がない。親類から届けられる野菜やインスタント麺は貴重なものだから自分たち家族だけでなく、同じ境遇に立たされている近所にも配っています。食料を持ち寄りみなで日々の糧をしのいでいるのです。」 共同生活に入る前は食料がまったくない飢餓状態なのかと怯えていたが、被災地域ぐるみで持つもの持たざるものがすべてを出し合って生活していた。ジョグジャカルタ市内の被害がない地域ではレストランやバーがすでにオープンしていて観光客の姿も目にする。そこから車で25分ほどのところでは瓦礫を掘り返して食事をまかなう人々がいる。このギャップに驚愕を覚えずに入られなかった。天災は避けられないものであると感じるもあまりの違いに自分だけでなく現地の人たちも信じられないと語っていた。しばらくの共同生活が続く。 (6月23日更新)
「運命」2006年6月4日
瓦礫の下から掘り返したビニールシートを使ってテントを設営する。長さ8メートルほどの巨大なものである。その中で眠る。気温日中34度、夜22度、特に夜は防寒服が必要なほどに寒さを感じた。にもかかわらず蚊が飛び回りいたるところを刺してくる。もっとも恐怖を感じたのは地震の余震が一晩に何度も繰り返されることであった。それも激しい揺れの震度4、5レベルのもので被災者たちはいつでも逃げ出せるよう身構えていた。毎日こうした夜をすごしている。睡眠も満足に取れない。午前4時過ぎにはイスラム教徒としてのお祈りが始まるので日の出前には起きている。被災地ゆえなのか、被災者たちは日々メッカに向かって深く祈りをささげていた。家族との約束どおり瓦礫の撤去作業を午前5時から始める。見事なまでに家屋が崩れ去っており、レンガをいくら撤去しても先がまったく見えない。夫と私、さらに近所の人たちで巨大な石や家具といったヘビーなものをとにかくその場からどかすことに明け暮れた。ショベルカーがないと無理だと思うものはハンマーやのこぎりで小さくしてから運び出した。 取材も大変であるがこの撤去作業というものはもっときついものである。汗だく、誇りまみれ、トラック10杯分は瓦礫があると夫は淡々と語る。崩壊した家屋に保険というものはあるはずもなく、こうした瓦礫を撤去した後は地面をならして崩壊した瓦礫を鉈で形を整えてふたたび組み立てていくという。家が完成するまで6年はかかると静かに語る。こうした生活の中でいったい何が一番必要なのかと問えば、やはり現金が必要であるという。 食料も水もテント暮らしも耐えることができる。とにかく生き残った2歳の子供のためにできることはすべてやってあげたい。そのためには絶望の中でのさらなる緊急時用の現金が必要なのだという。夫の仕事は大工、妻の仕事はパン焼き職人、地震以来収入は途絶え親類頼みの中で希望を抱くことは不可能と言いきれる。
戦争がある国、犯罪がある国、豊かな国、地震に襲われる国、これはすべて運命であると孫を失った祖父は語っていた。私たちにとって将来のビジョンを見据えることより、今を生きることのほうが大切なのだと毎晩聞かされた。娘を目の前でなくした父親はインタビューを取るたびに泣き崩れた。これ以上インタビューをとることはもうやめてほしいと言っていた。
99年のトルコ大地震、2004年のスマトラ沖地震、そして今回のジャワ地震、この三つの自らの体験取材を通して改めて地震大国日本に目を向けることが必要であると感じざるを得ない。今まで地震の準備をしておきましょうといわれても実感がわかなかった。今回のジャワ地震の被害を目の辺りにして危険回避のためにできることはやっておくべきだと気づかされた。(6月23日更新)

被災地での被害者が次々と緊急医療施設に運び込まれる。被災者の被害の特徴は下半身の骨折が大半を占めていた。

日本からの復興支援隊も現地入りしていた。自衛隊女性医療部隊も現地に駆けつけた。